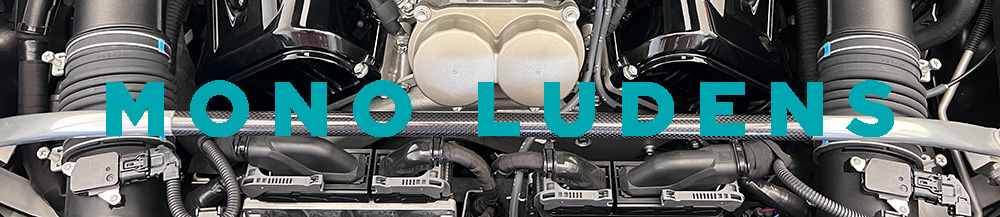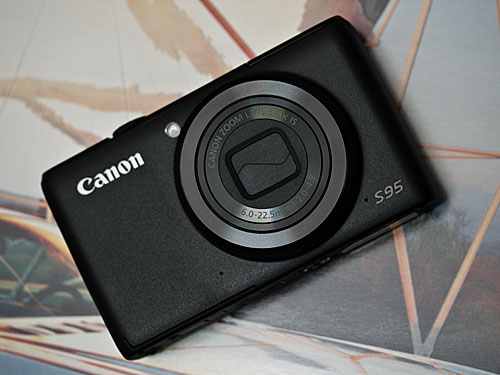(初出:2010/11/06)
最近キヤノンがやった英断に、業界の人はもっと拍手を送るべきだと思いました。
でも、自らの価値観にしがみつく老人達の声は以外に大きいらしい。
GR Digital IIIを最近ずっと持ち歩いています。
しばらくぶりの感覚を結構楽しんでいる私を発見したりして、自分でもけっこう意外でした。
そしてついに昨日。
レンズが出たまま戻らなくなってしまいました。
なんてこったい!
悪口書いたの、見たのかよ?
それでへそ曲げたのかよ?
思いっきり子供だな、おい?
どちくしょおおおおおおおおお!!ヽ(*`Д´)ノ
まあいいや。
所詮リコーのプロダクト。
中国で安く作っているということは、つまりはこういう事なんだろうなあ。
日本で、セル方式で、熟練の手先の器用なおばちゃんに作ってもらいたい!
そんでもって「このカメラは鈴木まりりんが心を込めてつくりました。可愛がってやって下さい」なんていうカードを箱に入れておいて欲しい。
たかがデジカメに重いな、おい?
とは多少思いつつも、そのGR Digital IIIがずっと機嫌良く動いていてくれたら、GR Digital IVが出た時、カメラ屋の親父にこういうと思う。
「鈴木まりりんさんのヤツで、頼むわ」
「ええ? 無茶言わんで下さいよ。まりりんさんのは入手困難なんですから。田中エリザベスさんとか、佐藤ナイチンゲールさんとかも評判いいですから、そっちで」
「それを言うなら佐藤フローレンスだ。ナイチンゲールは名字だろ? その人はちょっといただけないな。基本がわかってない」
「加藤小川って言う人もいますよ?」
「そいつのだったら返品するからな」
「評判いいのになあ……」
とまあ、そんな会話を楽しみながら、ご贔屓さんを作る楽しみもあるわけで。
勿論いろいろ問題があるでしょうし、既述したような芸名? でもいいと思います。
だったらあと二万円くらい高くても、私は喜んで買いますよ。
でもきっと、どこで誰がたとえトイレで手を洗わない人が作ったようなモノであろうと、妙な粉が吹いていようと、一円でも安ければそっちがいいんだろうなあ。
誰でも買える必要がないものだってあると思いますが。
それがあこがれっていうものじゃないのかな、とも思います。
でも、もうそんな時代じゃないんだろうなあ。
会社だって「ロマンでメシが食えるか」という感じなんでしょう。
寂しい時代だなって思います。
カメラの話じゃないんですが、世の中どんどんおかしい方向に向かっている気がします。
そう言えば親友Aが言ってました。
「バカに迎合してバカに歩調を合わせるバカな政府、それが今の日本」
百円ライター販売禁止とか、こんにゃくゼリーで喉を詰まらせて老人が死んだから、作った会社を糾弾して追い込むとか、なんか違うでしょ?
とと、脱線脱線。
そんなこんなで、実は私のGR Digital IIIはダメになってしまいました。
修理からかえってくるまで使えないということですね。
でも、リコーの場合、修理対応について今までイラっとした事はありませんでした。
対応はいいし、あのストロー式? 緩衝梱包材はいつ見ても秀逸です。
私のようなリコー修理常連さん? はあのストロー式を見ると「これこれ。これだよねー」とにっこりするに違いない。修理出しなのに。
ま、故障は世の連れ人の連れ(?)。
GR Digital IIIの本質とはまた違うもので、それはリコーの本質……と言う話はおいといて。
GR Digital IIIは一つの完成形だと思います。
初代から全部使っているし、その進化ぶりに対しては確かな進歩を感じます。
画質やレンズの描写性能は勿論大事だけれど、それ以前の問題としての「レスポンス」が心地いいんです。
質感や描写性能には一目置くもののP7000のようなカメラには、やっぱりシンパシィが生まれにくい。「普段使いには勘弁」という感じ。それは大きさを超えたネガティブ要素じゃないかとさえ思えます。
ジャケットの胸ポケットになんとか入るギリギリの大きさであるGR Digital IIIは、普通に町を歩いている時、気になったものやいいなって思ったシーンを撮る時にささっとその欲求を満たせるところがすばらしい。
GR Digitalだとこれがムリ。1枚目はいいとしても2枚目に行く時につまずいてしまう。
GR Digital IIでも微妙にムっとします。Jpeg+RAWがデフォルトの私だけの問題かもしれないけれど、RAW撮りできるカメラでRAW撮りしないなんて私の場合はあり得ない。
4000×3000をフル解像度とするデジカメでブログ用だからと言ってVGAでしか撮らない行為が私にとっては異文化なのと同様で、人それぞれスタイルが違うと感想も違ってくるとは思います。
でも、その点GR Digital IIIは合格です。
さっと取り出して電源ON。
構図を決めて合焦。
場合によってはフォーカス位置を移動させて合焦作業にはいるわけだけど、この辺のレスポンスがようやく人間の感覚にいらだちを感じさせないレベルに達したように感じます。
もちろんもっとAFは速くなるべきだし、書き込みも瞬時で終わって欲しい。P7000と違って書き込み途中で電源offにしても最後の一枚がエラーファイルになるなんて事はないのでアレだけど、何にせよ速くて困る事はないのですから(P7000が異常なのであって、最近のカメラでそういうエラーが出るのは珍しい)。
AFの合焦能力そのものはそれほど高いとは思いません。
伝統的に茶系の低コントラストな被写体には合焦しないままだし、雲も怪しいまま。
もっともこのあたりは撮像素子の大きさが違いすぎる4/3との比較なので厳しすぎる目かもしれないけど、P7000よりは数倍マシなのでストレスは少ないです。
R0010034.jpg
(GR Digital III)
レスポンスが速いのは七難どころか百難をも隠します。
その分被写体に集中できるから、撮影の満足感が増すわけですね。
そしてインタフェイス。
好みもあると思うけれど、コンパクトカメラのパラメータ調整メニューの作りを含めたインタフェイスとしてはリコーが一番いいと私は思います。
GXRもそうだけど、GR Digitalのメニューはいわゆる初心者にはかえって使いづらいんじゃないかと思えるほどパラメータが豊富でかゆいところに手が届く感じにはなっています(実はまだまだだと思うけど)。
パラメータへたどり着く方法も、慣れれば速い。というか、そういう風に作られているから、使い込んでいけば行くほど手になじむ感じがあります。
この辺もGR Digital IIIをはじめとするリコーのデジカメに一定数のファンがいる理由だろうなと感じるところ。
SONYのNEXチームはリコーを小馬鹿にせず(してるかどうか知りませんが)、真摯に学ぶべきだったと思います。
まねでもいい。いや、マネしてくれていたら、少ないボタンでもう少しまともに操作できる(している気になる、と書き換えてもいい)カメラが作れたんじゃないかと思うんですよ、NEX-5。
「写真はフィーリングですよ」なんて言ってるだけではいつまで経ってもかめら「もどき」しかつくれないんじゃないだろうか。
いや、売れたらなんでもいいでしょうが……。
だったらSONYの美学はどこへ行った? と言わざるを得ないわけですが。
カスタム設定が3つ。
それもモードダイアルに埋め込んであるのも大好きです。
私はいろいろ煮詰めたセッティングを決めると、ISOだけ変えて3種類登録しています。
こんな感じ。
my1:ISO Auto
my2:ISO Auto-Hi(1600まで許す、というカスタマイズ)
my3:ISO 64
そう。ISOだけかえて3種類登録。
「ISOなんて別のボタンに割り当てたらいいじゃーん」
と、昔は私も思っていました。だから用途別に登録していたりしたじきもありましたが、GR Digital IIの後期くらいからはこういう考え方になりました。
なぜなら「その方が速いから」
ISOのパラメータ変えるのは最低でも3回くらいボタンを押さないと目的のモノにたどり着かないでしょ?
でもこれだとある意味一回で目的に到達できるんです。
ISOが物理的な的として存在しているから選びやすいでしょ?
いえ、何をどうやっても人それぞれ好きなようにやればいいんでしょうけど、私のGR Digital IIIの使い方って基本プログラムオートでぱぱっととるスタイルなので、ISOいじって画質とぶれのバランスをとる事くらいが大きな仕事になるんです。
PASなんかのモードダイアルなんていらないくらい。my1~5くらいに変えて欲しいな、と。
そもそもPに入れておけば、ダイアルがあるカメラならプログラムシフトでどうとでもなるじゃん? なんでいちいちAとかSにするの? みたいな?
というスタイルなので。
だから通常はISO Autoの1番。
でも、GR Digital IIIのISO Autoってどうやら154という妙な数字までしか上がらないみたいなので、暗いなあーと思う場所では迷わず2番を選択。
MAX800でもいいかな、とは思うけど、個人的には1600でも写っている事が大事なので1600は許容範囲としてる。人によっては400まで、なんてのもアリだろうけど。
そしてカメラを固定して撮れる場合、固定して撮る場合は3番を選ぶ。
これでGR Digital IIIはよき「相棒」って感じになってくるんです。
結構お気に入りで使っているし、使っていて楽しいカメラだな、って改めて思います。
ただ、やっぱり気になる点、大嫌いな点をとりあえず2つ挙げておきます。
これはきっと「GRのアイデンティティですから」なんて勝手にでっち上げた亡霊に取り憑かれたような理由で無視されるとは思うけど、私のような「伝統は進化してより高みへ登るこそで伝統たりえるのではないのか?」と思っている人間のこんな意見もあるんだという事であえて書いておきます。
というか、GR Digitalの事書く度に毎回毎回同じ事の繰り返しだね。
★電源のON/OFFをボタン式からレバー式に改めろ!
電源ONの時の緑色点灯、という場末の安キャバレーみたいな電飾がON/OFFできるようになったのは進歩だけど、そもそもボタン式はダメだって。
プレミアム系のカメラだからこそ、レバー式にして欲しいぞ。
★長円形のシャッターボタンもやめれ!
ダサ過ぎる。
どっかの三流高校の文化祭の模擬店の焼きそばみたいだ(意味不明)。
で。
見てくれに関する要望だけど、GR Digital IIIを見ていて、使っていてつくづく思いました。
もう「Digital」の名前は取ろうよ。
EOS DigitalからDigitalの名をとったキヤノンの英断に、私は拍手を惜しまなかった。
時代はもうシフトした。いや、そもそもリコーはキヤノンやニコンよりずっと前から自らシフトし尽くしている。
ならばDigitalの文字なんて、レガシーなIOみたいなものだろう?
そう、中国のノートPCメーカー、レノボのノートPCについているパラレルポートみたいなものなんです。
フィルム時代のGRと区別するためにDigitalの文字を冠する意味はわかります。いや、わかりました。
でも、もう三代目ですよ、GR Digital。
だから、そろそろいいんじゃないかな。
GR Digital IIIの後継機が、GR Digital IVという名前じゃなく、Digitalを抜いた新しい名前になるといいな。
そうなってこそ真の意味での新しい時代のGRの誕生じゃないのかな?
中身は大切だけど、名前というのは本当に重要な記号なんだと私は信じています。