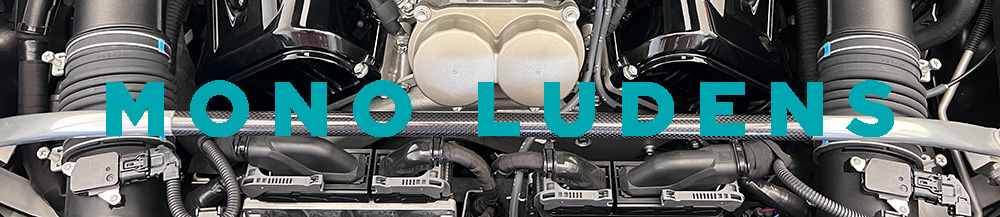(初出:2011/09/04)
BC
それは紀元前の事。ビフォア・キリストの略なのはみんな知っている事。
AD
それは西暦の事。アンノー・ドミニーの略なのは日本とアメリカのみんなは知っている事。
ではQに於けるBCとは?
それはボケ・コントロールの事。意訳すると「ぼけ防止」の意味だってことは私だけが知っている事。
まあ、そう言うわけで撮像素子が小さなQはコンパクトデジカメと同じ土俵に立っているので、ボケの絶対量を突っつかれると不利。
だったら画像処理でボケ、つくっちゃいましょ! 的なノリ機能を(今のところまだHOYAの)PENTAXは搭載してくれました。
私は黒か白かの二択を迫られるならば、「ボケなどどうでも良い」派です。
なのでさほどこだわりませんし、ボケが必要だと思ったらたとえばα900あたりを使います。
でも、Qで結構なボケ効果が出るなら、それはそれで楽しいし、表現の幅が広がるわけで、ウェルカム。まちがっても「搭載するな!」なんて思いません。
で、そのBCモードを色々試しているのですが……

(α900/Tamron 90mm Macro)
今のところの正直な感想としては
1)思ったより使える
2)被写体(シチュエーションと言うべき??)により、効果が変わる
というところ。
「作品」などと大上段に構えたらアレでしょうけど、私はそんなのどうでもいいので積極的に使おうかな、と思ってます。
欠点かな、と思うところは
1)RAW撮りはできず、基本敵にJpegモードになる
2)処理に結構時間がかかる
くらいでしょうか。
このBCモード、パラメータ的にはその「量」を三段階から選ぶだけというシンプルさです。
いろいろ試してみたところ、空間内に独立した物体が被写体だとさほど「アレェ?」感はないと思いますが、連続する物体の一部にピントが合っている場合なんかだと、ボケのエフェクトが入る境界線あたりに妙な違和感を覚える人もいるかもしれません。
とはいえ予想以上によく出来たエフェクトですし、よくここまでになったなあ、と思いました。
今後この機能はブラッシュアップされてさらに不自然さがなくなってくるでしょうし、ボケの状況を撮影者が文字通り細かく詳細に「コントロール」できるようになると思います。そうなると撮像素子の持つデメリットの一つが解消されるかもしれません。
だとするとシステム全体が小型軽量化できるわけですから、これは期待できる技術だと思いました。
ある意味、Qはミルクスだけでなく、システムカメラの入り口を示したエポックメイキングなカメラじゃないかという気がしてきました。